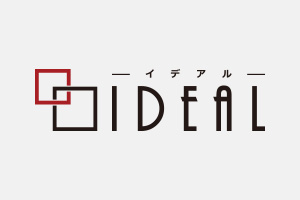本記事で、ガールズバー開業の流…
2017.06.10 2023.07.27|新規開業ノウハウ
本屋を開業する流れとポイント!業種・業態の基本情報や開業資金も紹介

本記事で、本屋を開業する流れとポイントを解説します。書籍・文房具小売業の基本情報や開業資金もご紹介します。店舗の開業や移転、リニューアルなどをご検討中の方は、ぜひご覧ください。
目次
本屋(書籍・文房具小売業)の基本情報

本屋(書籍・文房具小売業)の開業準備を始める前に、業種・業態の基本情報を確認しましょう。そこで本屋(書籍・文房具小売業)の基本情報として、業種の特徴と主な事業内容、業態の種類、市場規模をご紹介します。
業種の特徴
まず本屋の業種(書籍・文房具小売業)の特徴は、各出版社から書籍の販売を委託されている点や幅広い顧客層をターゲットにできる点などです。
各書籍の小売価格が決まっているため、競合店との価格競争が起こりません。また本屋の業種(書籍・文房具小売業)の特徴といえます。雑誌やマンガ、資格関連、小説などの本が販売されており、小売業の中で集客しやすいです。
ただし近年ではアマゾンや楽天などのオンラインストアでも書籍や文房具は販売されるようになったので、実店舗への集客は難しくなっています。本屋の集客方法については、後ほどご紹介します。
主な事業内容
次に本屋(書籍・文房具小売業)の主な事業内容は、書籍の仕入れと販売です。仕入れ業務には、本屋経営者の手腕が問われます。仕入れる商品(書籍や文房具など)の種類によって、集客できるターゲット層や利益率が変わるからです。
したがって開業する本屋のターゲット層の興味・関心を分析し、話題の書籍や売れ筋の文房具などの仕入れが求められます。仕入先の選定方法については、後ほどご紹介します。
なお販売業務においては、店舗内の商品陳列やキャンペーン・割引セールなどの検討が必要です。各書籍の売上や各出版社の出版状況などに応じて、定期的に販売方法の変更も求められます。
業態の種類
また本屋(書籍・文房具小売業)の業態には、実店舗とオンラインストアがあります。両者の違いを理解したうえで、本屋の事業目的に合う業態を選びましょう。
まず実店舗のメリットとして、顧客に商品を手に取ってもらうことで販売を促せます。しかし店舗物件取得や集客などにコストがかかる点は、デメリットです。
一方で本屋のオンラインストアのメリットとして、Web上で24時間営業できる点や実店舗よりコストがかかりません。ただしWebサイト運営やWeb集客のスキルが求められます。
市場規模
そして本屋(書籍・文房具小売業)の市場規模は、2000年代より減少傾向です。2000年に2万店舗以上が営業されていましたが、2020年には半分近くになりました。原因として、書籍のオンライン販売拡大や電子書籍の普及が挙げられます。
参照元:文化通信デジタル「【アルメディア調査】2020年 日本の書店数1万1024店に、売場面積は122万坪」
実店舗の大手チェーンとして、丸善や紀伊国屋、TSUTAYAなどの本屋があります。またAmazonや楽天などは、オンラインストアです。ただしオンラインストアを運営している実店舗の本屋もあります。
なおコロナ禍においては、巣ごもり需要から出版業界の売上は微増しました。ただし紙媒体の売上を減少し、電子書籍の売上が増加。今後も売上を伸ばすためには、電子書籍はもちろん、文房具などの書籍以外の商品販売も求められます。
参照元:日本経済新聞「出版市場22年2.6%減 巣ごもり需要終息し、4年ぶり減少」
本屋を開業する流れ

書籍・文房具小売業の基本情報を押さえたうえで、本屋を開業する流れを確認しましょう。コンセプト・事業計画から開業資金、店舗物件のデザイン・工事、資格、仕入先、商品陳列、防犯対策までの流れをご紹介します。
コンセプト設計と事業計画立案
まず本屋を開業する流れは、コンセプト設計と事業計画立案の作業から開始されます。本屋のコンセプトは店舗経営の基本方針となり、商品開発や内装デザインにおいて一貫性を保つために必要です。
そして設計したコンセプトに基づいて、事業計画を立案しましょう。本屋の事業目的や売上目標、資金計画などを事業計画書にまとめます。コンセプト設計と事業計画立案について纏めてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
開業資金を調達する
次に事業計画を立案できたら、本屋の開業資金を調達しましょう。自己資金だけで不足する場合には、以下の開業資金の調達方法を検討しましょう。
- 出資
- 借入
- 融資
- 補助金・助成金
以上の各調達方法には、利用できる条件やメリット・デメリットがあります。詳しく解説してありますので、次の記事も併せてご覧ください。
なお本屋開業資金の相場と内訳、節約法については、後ほど詳しくご紹介します。
店舗物件を探す
また実店舗を開業する場合には、資金調達を進めながら、本屋を開業する店舗物件を探す必要もあります。物件の規模や立地などは、集客と売上に影響します。販売したい書籍・文房具の種類や数量について、事前に計算しておきましょう。
特に立地選びを間違えると、集客効率を上げられません。例えば人通りの多いエリアでも、本屋のターゲット層が出入りしているとは限らないからです。そこで市場調査を踏まえて、出店エリアを絞る必要があります。
他にも店舗物件探しのコツをまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
店舗をデザイン・工事する
そして物件の購入・賃借を契約できたら、店舗をデザイン・工事します。顧客満足度を高めて売上を伸ばすためには、競合との差別化を図る店舗デザインが重要です。コンセプトに基づいて、各エリア(陳列や会計、バックヤードなど)をデザインしましょう。
なお店舗工事においては、信頼できる業者を選ぶことが必要です。本屋の内装をデザインするポイントや業者の選定、工事費用などについてまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
届出・許可を申請する
さらに実店舗の準備だけではなく、届出・許可を申請する作業も、本屋を開業する流れに含まれます。
まず個人事業主として本屋を開業するための届出・許可をご覧ください。
- 個人事業の開廃業等届出書(原則的に必要)
- 所得税の青色申告承認申請書 (税制上の優遇を受ける場合)
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(従業員を雇用する場合)
- 消費税課税事業者選択届出書 (課税事業者を選択する場合)
参照元:国税庁「No.2090 新たに事業を始めたときの届出など」
また法人を設立して本屋を開業するための届出・許可もご紹介します。
- 法人設立届出書(原則的に必要)
- 法人税の青色申告承認申請書 (税制上の優遇を受けたい場合)
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(原則的に必要)
- 消費税課税事業者選択届出書 (課税事業者に該当する場合)
そして新刊を仕入れて販売するためには届出・許可が必要ありませんが、古本を扱うためには古物商許可申請が必要です。
参照元:警視庁「古物商許可申請」
仕入先を選定する
それから開業3~6か月前には、仕入先を選定しましょう。良い商品を安く仕入れることで、売上に対する利益率を高めることができます。複数の業者と取引することで、商品の安定供給と価格交渉をしやすいです。
仕入先には出版業者や取次店があります。仕入れの方法は、委託販売(売れ残った商品の返品可能)と買い切り(卸値が安いが返品不可)です。各仕入業者から見積もりを取り、商品の種類や卸値、納期などを比較検討しましょう。
商品の陳列方法を決める
また仕入先から商品が納入される前に、商品の陳列方法を決めましょう。本屋における商品陳列方法をご覧ください。
- 平積み:表紙を表に陳列
- 面陳列:目線の高さに陳列
- 棚差し陳列:背表紙を見せて陳列
- 多面陳列:表紙も裏表紙も見せて陳列
上記の陳列方法によって、店内を回遊する顧客の動線が変化します。新刊やベストセラーを平積みにし、キャンペーン品を多面陳列することで、顧客の注目を集めやすいです。購買を促す陳列方法を検討しましょう。
防犯対策を講じる
なお本屋を開業する前に、防犯対策を講じなければなりません。調査機関の報告によると、本屋の万引き被害額は、1店舗当たり年間200万円程度と報告されているからです。本の利益は20%程度であるため、万引きの被害は本屋の利益率を下げます。
参照元:
一般社団法人日本出版インフラセンター「書店万引き調査等結果概要」(10ページ)
日経クロステック「書店連合が顔認証技術で万引き対策、法的問題をどうクリアした?」
そこで万引き対策として、防犯カメラやICタグなどを検討しましょう。ただし本屋で起こりうる犯罪は万引きだけではりません。店舗で発生する恐れのある犯罪と防犯対策するポイントをまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
本屋を開業する際のポイント

本屋を開業する流れだけではなく、集客と売上を伸ばせるように、本屋を開業する際のポイントも押さえましょう。本記事では、5点(市場調査と競合分析、商品・サービス開発、店内の動線設計、集客方法、DX)を取り上げます。
市場調査と競合分析
まず本屋を開業する際のポイントとして、市場調査と競合分析が挙げられます。市場調査と競合分析により、集客活動や営業活動の経営戦略の立案が可能です。そこで開業予定エリア内において、顧客のニーズや競合書店の営業状況などに関するデータを集めましょう。
そして市場調査と競合分析に基づいて戦略を立ててからも、定期的に本屋の経営状況を評価・改善することが重要です。社会情勢や周辺環境の変化に応じて、本屋に求められるニーズや業態は変化します。
商品・サービスの開発
次に商品・サービスの開発も、本屋を開業する際のポイントです。インターネットの発達や電子書籍の普及により、紙媒体の書籍を手に取る機会は減少しています。そこで紙媒体の書籍以外の付加価値を提供して、集客と売上を伸ばしましょう。
例えばTSUTAYAは、カフェやオフィスの機能を備えたラウンジを営業することで、書籍の売上だけではなく、ドリンクやスペース利用料の獲得を図っています。他にも雑貨やファッションなどと組み合わせた本屋の業態も可能です。
店内の動線設計
また店内の動線設計も、本屋を開業する際のポイントです。顧客と従業員の動線を確保することで、顧客満足度と業務効率の向上を期待できます。従業員の作業動線を短くして陳列や会計のスピードを上げると、丁寧な接客をしやすいです。
そして顧客が入店してから退店するまでの動線を長くすることで、商品を手に取る時間を伸ばすことができます。店舗の動線を設計する際の注意点をまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
集客方法の組み合わせ方
それから集客方法の組み合わせ方も、本屋を開業する際のポイントです。集客方法は、オンライン集客(オンラインストアやSNS広告など)とオフライン集客(雑誌広告や交通広告など)に分けられます。
例えば開業エリア内で交通広告を出稿し、広告内にオンラインストアのQRコードを記載しておくと、アクセス数の向上を期待できます。店舗の集客に成功した事例をまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
店舗経営のDX
なお本屋を開業する際のポイントとして、店舗経営のDXも欠かせません。店舗DXとは、「デジタル技術による店舗経営の仕組みや商品・サービスなどの変革」です。集客と売上を伸ばすために、デジタル技術を駆使しましょう。
例えば本の検索システムや無人レジなどを導入すると、顧客が商品を探しやすくなったり、従業員が業務をしやすくなったりします。店舗DXの方法や費用、事例などをまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
本屋の開業資金

まず本屋の開業準備を進めるためには、開業資金が必要です。そこで本屋の開業準備を始める前に、開業資金の相場と内訳を把握しましょう。無駄な経費を削減できるように、開業資金の節約法もご紹介します。
相場
本屋開業資金の相場は、坪単価50万~100万円程度です。20坪の物件なら、1,000万~2,000万円程度かかります。ただし店舗物件の立地や規模、従業員数、商品の種類などによって、開業資金は変動します。
内訳
次に本屋開業資金の内訳について、下表にまとめました。参考情報として、スケルトン物件(20坪で賃料月20万円)に本屋を開業する費用の内訳を試算してあります。
| 資金の内訳 | 各費用の目安 | 費用の試算 (20坪で賃料月20万円の スケルトン物件) |
| 物件取得費 (敷金・礼金・前賃料など) | 全体の10%程度 (賃料6〜10ヵ月程度) | 100万~200万円程度 |
| 店舗工事費 (内装・外装など) | 全体の30%程度 (坪単価10万〜30万程度) | 300万~600万円程度 |
| 設備・機器・什器費 | 全体の30%程度 | 300万~200万円程度 |
| 集客・採用費 | 全体の10% | 100万~200万円程度 |
| 諸経費 | 全体の10% | 100万~200万円程度 |
| 運転資金 (開業後の固定費) | 全体の10% | 100万~200万円程度 |
| 合計 | 100%坪単価 50万~100万円程度 | 1,000万~2,000万円程度 |
上表のとおり店舗の工事・設備・機器・什器にかかる費用が、開業資金全体の半分以上を占めます。そのため開業資金を抑えるためには、実店舗にかかる費用を抑えることが必要です。
節約法
そして本屋開業資金の節約法として、居抜き物件の活用があります。前借主が施工した内装や設備・機器・什器を引き継げるため、工事費用を節約できるからです。ただし居抜き物件にはメリット・デメリットがありますので、次の記事も併せてご覧ください。
また店舗の開業・経営に活用できる補助金や助成金の申請も、本屋開業資金の節約法です。店舗の設備投資や人材の採用と育成、コロナ対策、個人事業主が活用できる補助金・助成金などがありますので、次の記事も併せてご覧ください。
集客できる本屋を開業しよう!
IDEALは、店舗全般のコンセプト設計から資金調達、物件探し、内外装のデザイン・工事、集客までのワンストップソリューションをご提供しております。
下のキーワードをクリックして、店舗デザインや開業準備などの関連記事もぜひご覧ください。また店舗の開業や移転、リニューアルなどをご検討の際は、ぜひご相談ください。
監修者
-
IDEAL編集部
日本全国の美容室・カフェ・スポーツジム等の実績多数!
> IDEALの編集者ポリシー
店舗づくりをプロデュースする「IDEAL(イデアル)」が運営。
新規開業、店舗運営のお悩みや知りたい情報をわかりやすくお届けいたします。