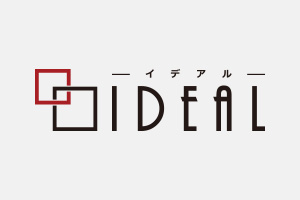本記事で、焼肉フランチャイズの…
2018.08.27 2025.01.23|新規開業ノウハウ
ラーメン屋経営は儲かる?廃業率・厳しい理由・戦略・事例を紹介

本記事で「ラーメン屋経営は儲かる?」という疑問にお応えするために、ラーメン屋経営の廃業率・厳しい理由・戦略・事例などをご紹介します。店舗の開業や移転、リニューアルなどをご検討中の方は、ぜひご覧ください。
目次
ラーメン屋経営は儲かる?基本情報を紹介

どれくらいラーメン屋経営は儲かるのでしょうか?そこでラーメン屋経営の基本情報(市場規模と儲かる理由、経営者の年収、廃業率・倒産件数)をご紹介します。ラーメン屋経営の実態を把握したうえで、開業を検討しましょう。
市場規模と店舗数
まずラーメン屋の市場規模は以下の資料によると4,400億円程度で、店舗数は全国に2万以上です(2021年)。コロナ禍(2020~2022年)に飲食サービス業界全体の市場規模が落ち込みましたが、2023年より回復傾向にあります。
参照元:
富士経済「ファストフードやテイクアウトなど 6 カテゴリー63 業態の
都道府県別統計とランキングで見る県民性「都道府県別ラーメン店舗数」
日本フードサービス協会「外食産業市場動向調査令和 5 年(2023 年)年間結果報告」
ラーメン屋の市場規模と店舗数は、2023年以降も拡大すると予想されます。ラーメン好きの日本人からはもちろん、インバウンドからの需要があるからです。
参照元:
LASISA「【SNS】『2024年“ラーメン”何杯食べました?』 農水省が突然のアンケート調査… 気になる結果は」
ロケットニュース「【秋葉原】インバウンド客たちが行列を作るラーメン屋を見て「ここ?」ってなったが食べたら納得した」
儲かる理由
次にラーメン屋経営が儲かる理由は、安定した需要や原価率の低さ、回転率の高さなどです。日本人やインバウンドからの需要が安定しているため集客がしやすく、メニューを絞れば原価率を抑えやすくなります。
フルサービスのレストランと比べると、注文を受けてからメニューを提供して顧客が退店するまでの時間が短いため、ラーメン屋の回転率は高くなります。ラーメン屋の回転率を高める方法をまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
経営者の年収
それからラーメン屋経営者の年収は、Web上に掲載されていませんでした(2024年12月時点)。以下のページによると300万円から1,500万円程度だと推測されますが、店舗の立地や規模、営業日数、店舗数などによって経営者の年収は変動します。
参照元:飲食店ドットコム「飲食店経営者の『年収』や『悩み』をアンケート調査。赤字店の98.1%が『集客力』に課題」
例えばラーメン屋(月間売上130万円で利益率30%)を2店舗経営するなら、経営者の年収は1,080万円程度です。
- 月間売上150万×12ヵ月×2店舗×利益率30%=1,080万円
廃業率・倒産件数
そしてラーメン屋経営の廃業率はWeb上に掲載されていません(2024年12月時点)が、ラーメン屋の倒産件数は45件(2023年)でした。以下のページによると、閉店したラーメン屋の90%以上が10年以内に閉店しています。
ラーメン屋の倒産件数はコロナ禍(2020~2022年)に減少傾向にありましたが、2023年から増加傾向です。コロナ対応の補助金・助成金給付の終了や物価高などが要因として挙げられています。
参照元:
飲食店ドットコム「閉店したラーメン店、4割がオープンから1年以内に営業終了。飲食店で閉店しやすい業態とは?」
東京商工リサーチ「2024年1-9月のラーメン店倒産 47件で年間最多を更新中」
ラーメン屋経営が厳しい理由

基本情報を把握しうえで、ラーメン屋経営が厳しい理由も確認しましょう。ラーメン屋の経営戦略を立てるためです。それでは6点(初期投資の高さと競合店の多さ、独自性の出しづらさ、価格の上げづらさ、原価率の高騰、人手不足)に整理して、ご紹介します。
初期投資の高さ
まず初期投資の高さが、ラーメン屋経営が厳しい理由として挙げられます。軽飲食店(カフェやスナックなど)と比べて、重飲食店のラーメン屋には大型の厨房設備・機器が必要だからです。
ラーメン屋の集客・売上が安定せずに投資回収が遅れるほど、店舗の休業・廃業のリスクが高まってしまいます。そこで資金の調達やコストの削減などのポイントについて、後ほどご紹介します。
競合店の多さ
次に競合店の多さも、ラーメン屋経営が厳しい理由です。全国に2万軒以上あるラーメン屋だけではなく、中華料理屋やファミリーレストラン、居酒屋などの店舗もラーメンを提供しています。
参照元:都道府県別統計とランキングで見る県民性「都道府県別ラーメン店舗数」
自店舗のエリア内で営業している競合店が多いほど、集客と売上を伸ばしづらくなります。競合店の少ないエリアを選んでも、必ずターゲットとする顧客層を集客できるとは限りません。そこで商圏調査・立地選定について、後ほどご紹介します。
独自性の出しづらさ
それから独自性を出しづらさも、ラーメン屋経営が厳しい理由です。各店舗で、定番の味(醤油・味噌・塩・豚骨など)やトッピング(チャーシュー・玉子・ネギ・メンマなど)のラーメンが提供されています。
参照元:
dポイントクラブ「みんなラーメンが好き?人気の種類やトッピングなどを大調査!」
定番の味やトッピングのラーメンだけを提供する場合には、集客数を増やすために競合店との価格競争に巻き込まれるリスクを抱えてしまいます。そこでメニュー開発・ブランディングについて、後ほどご紹介します。
価格の上げづらさ
また価格の上げづらさも、ラーメン屋経営が厳しい理由です。以下の調査によると1杯1000円以上するラーメンに対して消費者が抵抗を感じているため、ラーメンの価格を上げづらい状況にあります。
参照元:
日刊SPA「ラーメン店の倒産が過去最多に。個人店が苦戦する中、規模を拡大する“人気チェーン”の存在感」
原価率(原材料費や人件費など)が上がっても販売価格を据え置くと、売上に占める利益率を下げてしまいます。販売価格を上げると、集客数を下げるリスクが高まります。そこで集客活動やコストの削減について、後ほどご紹介します。
原価率の高騰
さらに原価率の高騰も、ラーメン屋経営が厳しい理由です。以下の調査によると9割以上の飲食店が原価率の高騰を実感しており、6割の飲食店が原価率の目標を達成できていません。
参照元:
PR TIMES「飲食店の98%が物価高騰を実感。68%がメニューを値上げも、客足への影響はほぼなし」
飲食店ドットコム「飲食店の原価率の実態は? 物価高騰の影響を受け、約6割の店舗が「目標より高い」と回答」
ラーメン屋の原価には原材料費や人件費、光熱水道費、宣伝広告費などが含まれ、原価率が高くなるほど売上に占める利益率が下がります。そこでブランディングやコストの削減について、後ほどご紹介します。
人手不足のなりやすさ
そして人手不足のなりやすさも、ラーメン屋経営が厳しい理由です。以下の調査によると、6割の飲食店で正規雇用の人材が不足しており、8割の飲食店で非正規雇用の人材が不足しています。
参照元:TDB Economic Online「人手不足に対する企業の動向調査(2023年4月)」
精神的なストレスや肉体疲労が伴う業務を任せたり、満足する雇用条件を提示しなかったりすると、求人応募数や採用定着率を下げてしまいます。そこで人材育成・マニュアル作成について、後ほどご紹介します。
ラーメン屋経営戦略のポイント

ラーメン屋経営が厳しい理由に対する解決策として、経営戦略のポイントを確認しましょう。6点(資金調達・投資回収と商圏調査・立地選定、メニュー開発・ブランディング、集客活動、コストの削減、人材育成・マニュアル作成)に整理して、ご紹介します。
資金調達・投資回収
まず資金の調達が、ラーメン屋経営戦略のポイントとして挙げられます。開業前の初期投資(物件取得費や設備・機器・什器購入費など)や開業後の運転資金(人件費や光熱水道費など)を計算したうえで、資金を調達しましょう。
予定どおりに投資回収を進めるためには、初期投資の削減や損益分岐点・キャッシュフローの確認なども重要です。店舗経営で投資回収するポイントをまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
商圏調査・立地選定
次に商圏調査・立地選定も、ラーメン屋経営戦略のポイントです。商圏(店舗のターゲットとする顧客層が居住するエリア)の特性や競合店の営業状況などを分析して、自店舗のラーメンを求める顧客層が居住するエリア(自店舗の商圏)を特定しましょう。
商圏調査を踏まえて地域性や交通の利便性、通行量、視認性、競合店数などを分析したうえで、ラーメン屋を開業する立地を選定します。店舗を開業できる立地の種類をまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
メニュー開発・ブランディング
それからメニュー開発・ブランディングも、ラーメン屋経営戦略のポイントです。メニューを開発する際には、フレームワークの活用やコンセプトに基づいた店舗デザイン、異業種や他業態とのコラボ、スピード感、効果検証などのポイントを押さえましょう。
ブランディングを展開して消費者からの認知度や信頼感が高まれば、集客と売上の安定や集客コストの削減、人材採用率のアップなどにつながります。店舗をブランディングする流れと方法をまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
集客活動
また集客活動も、ラーメン屋経営戦略のポイントです。店舗へ集客する方法には、オンライン集客(WebサイトやSNS、MEOなど)とオフライン集客(看板や交通広告、ポスティングなど)があります。
例えばSNS集客の成果を上げるためには、ターゲット層に合うSNSの種類を選び、SNSの運用状況を評価・改善しましょう。店舗のSNS集客を展開するコツをまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
コストの削減
さらにコストの削減も、ラーメン屋経営戦略のポイントです。利益率を高めるために原価率の低いメニューと高いメニューを把握して、メニュー全体の原価率を調整しましょう。フードロスの削減やオーバーポーションの防止も重要です。
メニューごとだけではなく、経費の項目(水道光熱費や人件費)ごとに無駄を削減することも必要です。アウトソーシングやDX、節税、料金プランの見直しなどがあります。店舗経営における経費削減方法をまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
人材育成・マニュアル作成
そして人材育成・マニュアル作成も、ラーメン屋経営戦略のポイントです。採用率や定着率を高めるためには、採用したい人物像を明確にしたうえで、求職者にとって魅力的な雇用条件を提示して採用活動を展開しなければなりません。
採用した従業員が円滑に業務を遂行できるように、調理や接客などに関する研修を計画します。研修前には、顧客からのクレーム対応やメニューごとのレシピなどをマニュアルにまとめておきましょう。
ラーメン屋の経営事例
ポイントを押さえてラーメン屋の経営戦略を立てられるように、参考となる事例を調査しましょう。事例5点を取り上げて、各事例の特徴(出資と駅チカ、独自メニュー、セントラルキッチン、外国人材)をご紹介します。
出資で資金調達したラーメン屋
まず「東京海老トマト早稲田店」は、出資で資金調達したラーメン屋です。新宿店で修業をした学生が、知り合いの会社経営者からの投資で開業資金(1,000万円程度)を調達しました。
中国人留学生の顧客が増えているため、日本語・英語に加えて中国語の発券機設置が予定されています(2024年7月時点)。イタリアのフルーツトマトが使用された独自性のあるラーメンを提供するラーメン屋の経営事例です。
参照元:早稲田ウィークリー「『東京海老トマト』を出店した早大生 ラーメン愛で早稲田文化の担い手に」
駅チカに立地するラーメン屋
次に「麺屋EDITION草津店」は、駅チカに立地するラーメン屋です。最寄駅から徒歩数分の立地で、交通の利便性が高いです。滋賀県に初出店でしたが、開業から4ヶ月で3万人以上の顧客が訪れました。
開業前には先行レセプションイベントが開催され、先着100名に無料でラーメンが提供されました。京都の食材(京丹波高原豚や九条ネギなど)が使用された背脂醤油ラーメンを提供するラーメン屋の経営事例です。
参照元:ビッグローブニュース「京都背脂醤油ラーメン店『麺屋EDITION』滋賀県初出店 JR草津駅徒歩3分の好立地に、2024年10月11日(金)より新オープン」
独自メニューでブランディングしたラーメン屋
それから「新御茶ノ水 萬龍」は、独自メニューでブランディングしたラーメン屋です。多店舗展開されていますが、各店舗に異なる名称が付けられており、メニューや味付けの裁量が各店長に与えられています。
「肉玉炒飯」を取り上げた地域の町中華イベントをきっかけにSNSでバズり、テレビ番組で取り上げられました。人材不足解消のために調理ロボを導入するラーメン屋の経営事例です。
参照元:ライブドアニュース「大阪王将が『町中華』を別ブランドで出す深い意味」
セントラルキッチンでコスト削減を図るラーメン屋

続いて「町田商店」は、セントラルキッチンでコスト削減を図るラーメン屋です。メニューの品質を保つために、自社工場・キッチンで製造された麺とスープが、各店舗に配送されています。
セントラルキッチン方式で、豚骨醤油の家系ラーメンが提供されています。入店時の挨拶やお礼の言葉、退店時の見送りなどを心がけているラーメン屋の経営事例です。
参照元:Foodslabo「家系で天下取り!?-町田商店がコロナ禍でもラーメン店で一人勝ちできた理由-」
外国人材を育成するラーメン屋

そして「フジヤマ55」は、外国人材を育成するラーメン屋です。外国人技術者派遣会社とフランチャイズ契約を結んで、ミャンマーへの出店を計画しています(2024年11月時点)。日本で就労を望む外国人材を雇用する予定です。
日本国内での就労が円滑に進むように、店舗責任者には日本で就労経験のある外国人が配置され、従業員同士の会話を日本語に限定する予定です。日本全国やアジア、ヨーロッパに展開しているラーメン屋の経営事例です。
参照元:
中部経済新聞「技術者派遣のサンテクノ ミャンマーにラーメン店出店 日本就労希望者実践教育の場に」
ラーメン屋の経営戦略を立案しよう!
IDEALは、店舗全般のコンセプト設計から資金調達、物件探し、内外装のデザイン・工事、集客までのワンストップソリューションをご提供しております。
下のキーワードをクリックして、店舗デザインや開業準備などの関連記事もぜひご覧ください。また店舗の開業や移転、リニューアルなどをご検討の際は、ぜひご相談ください。
監修者
-
IDEAL編集部
日本全国の美容室・カフェ・スポーツジム等の実績多数!
> IDEALの編集者ポリシー
店舗づくりをプロデュースする「IDEAL(イデアル)」が運営。
新規開業、店舗運営のお悩みや知りたい情報をわかりやすくお届けいたします。